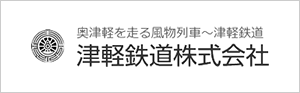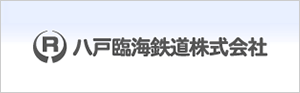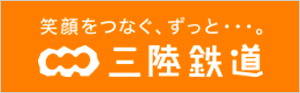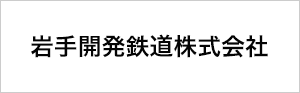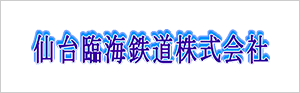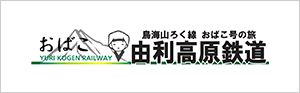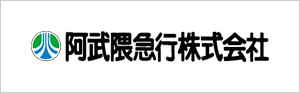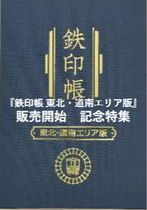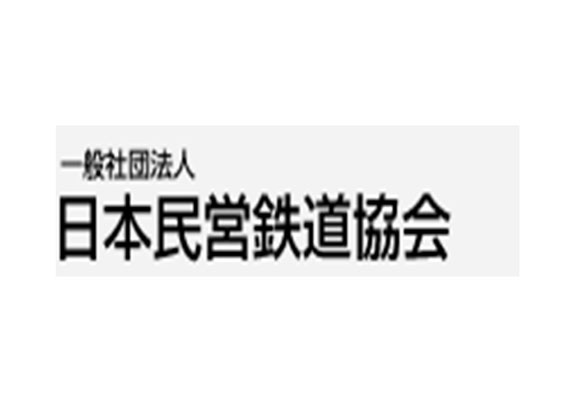仙台在住の伊藤謙信さんから、昨年の8月26日の本ページ(「鉄たびインフォ」)に『アドベンチャー路線 会津線』を寄稿頂き掲載しましたが、同氏から昨年末に第2弾の寄稿がありましたので紹介いたします。
※『アドベンチャー路線 会津線』はコチラ
古豪車両がんばる 弘南鉄道(弘南線・大鰐線)

青森県弘前市を中心に2路線で地域の足として活躍している弘南鉄道線。現在は弘南線と大鰐(おおわに)線があります。かつては弘前から2駅北の川部から現在の弘南線の終点黒石駅まで、国鉄黒石線を引き継いだ黒石線を有していました。地方鉄道では3路線も保有し、それぞれ特色の違う路線で、ファンとしてはとても乗っても撮っても楽しい路線でした。残念ながら黒石線は1998年に廃止されましたが、国鉄から民営鉄道が引き取る非常に珍しい例でした。黒石駅からは電車の弘南線、黒石線のディーゼル気動車で弘前に向かうことができ、地方都市では非常に珍しく画期的(ある意味活気)のある鉄道線でした。黒石駅では電車から気動車へ乗り換えもでき、たった2駅でしたが、国鉄から譲渡した気動車で夏は窓を開け、田園を一直線に快走し、冬は古い気動車特有の臭い(排気の臭い個人的には良い臭いです)で暑すぎるくらいの車内で床にワンカップ酒を置くと、すぐに「ぬる燗」になる車両でした。とても懐かしいです。

現在の弘南線はJR弘前から先述の黒石市の黒石まで約16キロを30分くらいで結ぶ路線です。弘前駅は近代的なJR駅と共用でホームも新しく、すぐ隣に奥羽本線があります。弘前駅で弘南線の車両がホームに入ってくるときは最徐行で入ってきます。初めて見る人は、ステンレス製の車両で新しい?と思ってしまうかもしれませんが、この車両は元東急東横線などで活躍した中間車(先頭車ではなく真ん中の車両)に運転台を改造して付けた車両です。乗ってみると、東京の「むかしの匂い」があちらこちらで感じられます。やけに多いつり革、広告スペースなどなど、古い車両に乗ったらチェックして欲しい箇所です。連結した車両の間に製造した年が貼ってある楕円の銘板があります。特に弘南鉄道の車両は座りながら窓から見ることができます。いまのJRや私鉄で連結面に窓がある車両も珍しいので、是非見て欲しいです。銘板には製造した会社と製造年が書いてあります。弘南鉄道の車両は昭和38年製ごろの車両がいまも元気に走っていて、元気をもらえます。もう60歳、1回目の東京オリンピックのころからの車両です。ちなみにこの車両は日本初のステンレス車両で由緒のある車両でもあります。

弘前を発車すると奥羽本線から別れすぐに高校のある駅、次に運動公園の駅、年1回楽天戦がある「夢はるか球場」の最寄り駅がありますが、開催時に臨時列車もあるようなので増結して長い編成での走行が見てみたいですね。次の駅には「9600型」SLが保存されていて、かなり保存状態が良い貴重なSLです。青森には「9600型」のSLが似合いますね。次の平賀がほぼ中間点の大きな駅で車庫があります。現在はほぼ元東急のステンレス車になっていますが、オリジナルの顔の車両や、赤い見るからに古そうな機関車と真っ黒い機関車?と思う車両があります。この車両はキ100型の除雪車で、現在ではこの除雪車が動いているのは弘南鉄道と津軽鉄道のみです。始発前などに走ったりするので、なかなか走行するところを見ることは厳しいですが、約100年前に製造されたアメリカ製の赤い電気機関車の走行シーンはまさに昭和30年代の風景です。列車を1本遅らせて、駅のホームから観察や撮影もおススメです。
平賀を出ると住宅地を抜け、広大な田園地帯を走ります。一部高架線のようなところから見る岩木山が、私は一番のビューポイントだと思っています。特に晴れた冬は一面の銀世界に岩木山、晴れ日にあたれば抜群の景色です。余韻に浸っていると左側から昔、線路があった感じの線路跡が寄り添って来ると終点黒石です。黒石では「黒石やきそば」を食べて帰りましょう。ちなみに20年前に仙台駅在来線4・5番ホームの「駅そば」屋で「黒石やきそば」が食べられました。店員さん曰く当時の社長さんが「黒石やきそば」が気に入り提供していたのだとか、店員さんはスピード勝負のホーム「駅そば」で作るのが大変と笑っていました。とても美味しかったです。

さて、もう一つの路線の大鰐線。このコラムを書いているときに、2026年に運行休止との報道があり、がっかりしたところですが、休止なので、廃止ではないので応援したいです。初めて乗る方はJR弘前からすぐに乗り換えできるかな?と勘違いしてしまいますので要注意です。発車する駅は弘前城の方角にある商店街の一角にものすごく風情のある駅舎です。こちらが「中央弘前駅」です。間違いのないようにお気をつけください。木造ではないのですが、どこかわくわくする旅情のある昭和感たっぷりの駅舎です。昔、にぎわっていた頃は「駅そば」や売店などがあったのだろうと思う駅舎内、切符を売る窓口、昔ながらの「発車時刻表」、「発車5分前から改札します」の表示がある改札口。交通カードしかしらない都会の若い方はある意味戸惑うかもしれません(笑)。ホームは1面1線ですが、そばに川が流れているので、車両と川の写真は駅舎の外から撮ると良い雰囲気で撮れます。上信電鉄の前橋中央駅に似ている感じがします。駅員さんの「改札します」の放送で改札の柵が開けられ、切符を渡し検札するのももう懐かしい光景です。


車両は弘南線と同じ車両が活躍していますが、製造した会社が違うので、マニアックな方はステンレスやビス打ちの違いが分かります。ホームも古くて良い雰囲気です。発車をすると市街地をくねくね曲がりながら進んでいき、地域の方の足と感じられます。この場所に駅?というところもあります。市街地を過ぎると「りんご畑」を進んでいきます。青森らしい風景で、思わず立ってドアの窓越しから「りんご畑」越しに岩木山を見てしまいます。弘南線とはまた違った印象を持つ大鰐線です。田んぼの弘南線、りんご畑の大鰐線という感じでしょうか。まもなく中間地点の車庫のある津軽大沢です。この駅にも赤い電気機関車と除雪車があります。また、ちょっと形の違ったステンレス車両が保存されています。元東急の6000系があります。現行の車両よりデザインが凝った車両でした。かつては「快速」に主に使用された車両で、地方鉄道で「快速」列車を運転するなど、ファンには嬉しい路線でした。現在の車両は元東急の車両になっていますが、特に大鰐線はむかしは「動く鉄道博物館」と呼ばれるくらいの車両が走っていました。省電(国鉄)時代の旧型電車ほか関西の私鉄、信州の私鉄、西武線など、譲渡された全ての車両を、雪国でメンテナンスも大変だったと思いますが、大事に使っていました。
現在の大鰐線の車両もつり革にはあえて「東急百貨店」「渋谷」の文字などを残しています。また、1つだけりんごの形のつり革もあり、それを見つけると幸せ?になるそうな(笑)。是非、乗っている間に探してみてください。津軽大沢を出ると、義塾高校前、石川と止まります。石川は少し離れていますがJRの駅もあります。石川を出ると奥羽本線を大鰐線がまたぎます。ここが電車の撮影がキレイに撮れると思います。運がよければJR車両を重ねて撮影ができるかもしれません。列車の本数が少なくないのでチャンスは少ないです。大鰐線は終点を目指しラストスパートののんびりした速度で終点大鰐に到着します。JRは大鰐温泉という駅名になっている通り、良質の温泉があります。弘前からJRは約10分で到着しますが、約30分かけて地元の方言などを聞きながら、ゆっくりのんびり大鰐線で温泉を目指すのも良いかもしれません。
大鰐線も休止が発表されましたが、まだまだ地元の方の利用、観光客の利用が増えるように、応援したいです。がんばれ大鰐線
2024.12.24
伊藤 謙信